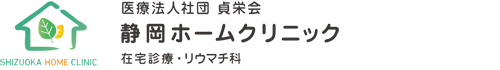介護保険の利用を申請する
在宅医療を始めるにあたっては、在宅医を探すことと併せて、介護保険の申請も重要です。
すでに介護保険のデイサービスなどの利用を始めていて、在宅医療を行っていなかったという人は、担当のケアマネジャーに在宅医療を始めたいとの希望を伝えてください。
地域の在宅医を紹介してもらえることもありますし、また、ご家族が探した在宅医をケアマネジャーに伝えるのでも構いません。
一方、まだ介護保険の申請手続きをしていないという人は、自治体の窓口で早めに申請をしましょう。
訪問介護や訪問看護といった介護サービスを受けたり、在宅療養のために住宅改修をしたりする際には、あらかじめ介護保険の申請をして要介護認定を受けておく必要があります。
すでに介護保険のデイサービスなどの利用を始めていて、在宅医療を行っていなかったという人は、担当のケアマネジャーに在宅医療を始めたいとの希望を伝えてください。
地域の在宅医を紹介してもらえることもありますし、また、ご家族が探した在宅医をケアマネジャーに伝えるのでも構いません。
一方、まだ介護保険の申請手続きをしていないという人は、自治体の窓口で早めに申請をしましょう。
訪問介護や訪問看護といった介護サービスを受けたり、在宅療養のために住宅改修をしたりする際には、あらかじめ介護保険の申請をして要介護認定を受けておく必要があります。
①自治体の窓口や地域包括支援センターで申請
介護保険の申請は、住んでいる自治体の介護保険の窓口や、地域包括支援センターで行います。
「地域包括支援センター」とは、高齢者に関するさまざまな相談を受け付ける拠点です。2012年時点で、全国の自治体4300カ所余りに設置されています。
同センターには社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーといった専門職の職員がいて、高齢者の福祉・医療・介護についての支援を行っています。
介護保険の申請は原則として本人または家族が行います。
しかし、何らかの事情でそれが難しい場合は、地域包括支援センターに申請を代行してもらうことが可能です。
「地域包括支援センター」とは、高齢者に関するさまざまな相談を受け付ける拠点です。2012年時点で、全国の自治体4300カ所余りに設置されています。
同センターには社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーといった専門職の職員がいて、高齢者の福祉・医療・介護についての支援を行っています。
介護保険の申請は原則として本人または家族が行います。
しかし、何らかの事情でそれが難しい場合は、地域包括支援センターに申請を代行してもらうことが可能です。
介護保険の申請に必要な書類
・要介護・要支援認定申請書
(用紙は自治体の窓口や、地域包括支援センターにある。自治体のホームページからダウンロードすることも可能)
・介護保険の保険証
(65歳になった時点で交付される)
・医療保険の保険証
・このほか、認知症の疑いのある方では病院の「物忘れ外来」などで診断を受けておくと、本人の実情に合った認定を受けやすくなります。
(用紙は自治体の窓口や、地域包括支援センターにある。自治体のホームページからダウンロードすることも可能)
・介護保険の保険証
(65歳になった時点で交付される)
・医療保険の保険証
・このほか、認知症の疑いのある方では病院の「物忘れ外来」などで診断を受けておくと、本人の実情に合った認定を受けやすくなります。
②訪問調査などののちに、1カ月ほどで要介護認定が決定
申請を出したのちに、役所の調査員が高齢者本人の自宅や病室へ来て、介護の必要度についての確認・調査を行う訪問調査があります。
この調査では、高齢者の歩行や立ち座りなどの身体機能、食事や排泄、衣服の着脱といった日常生活の自立度に加え
意思伝達、理解・記憶といった認知機能など、さまざまな点をチェックします。
このとき、高齢者本人だけでは実情をうまく伝えられないことが多いので、
高齢者の状態をよく知っている家族が立ち会い、具体的な情報を補うといいでしょう。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターによる一次判定があり、
さらに介護認定審査会による二次判定を経て、要介護認定が決定されます。(下図「要介護認定の流れ」参照)
申請から決定までには、平均して1カ月ほど時間がかかります。
この調査では、高齢者の歩行や立ち座りなどの身体機能、食事や排泄、衣服の着脱といった日常生活の自立度に加え
意思伝達、理解・記憶といった認知機能など、さまざまな点をチェックします。
このとき、高齢者本人だけでは実情をうまく伝えられないことが多いので、
高齢者の状態をよく知っている家族が立ち会い、具体的な情報を補うといいでしょう。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターによる一次判定があり、
さらに介護認定審査会による二次判定を経て、要介護認定が決定されます。(下図「要介護認定の流れ」参照)
申請から決定までには、平均して1カ月ほど時間がかかります。

要介護認定の流れ
要介護の状態区分と、心身の状態の例
要介護認定区分には要支援1~2、要介護1~5の7段階があり、それぞれの段階ごとに受けられる介護サービスの枠が決まっています。
・要支援1
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、一部で身体機能や生活能力の低下があり、介護予防のための支援が必要。
・要支援2
要支援1よりも、基本的な日常生活能力がわずかに低下した状態。
機能の維持や改善のために、何らかの支援が必要。
・要介護1
立ち上がりなどに支えが必要になり、歩行も不安定に。
排泄や入浴などの生活の一部で介助が必要な状態。
・要介護2
立ち上がりや歩行が自力では困難になり、排泄や入浴などで多くの介助が必要になる。
調理、金銭管理などに不安が表れるケースもある。
・要介護3
立ち上がりや歩行などが自力ではほとんどできず、排泄、入浴、衣類の着脱など生活全般に介助が必要。
物忘れなどが進む。
・要介護4
日常生活能力全般が低下し、食事や排泄、入浴、衣類の着脱などに全面的な介助が必要。
理解力の低下、問題行動が表れることも。
・要介護5
日常生活や身の回りの世話などの全面的な介助が必要。いわゆる寝たきりの状態。
記憶力、理解力の低下、問題行動が表れることもある。
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、一部で身体機能や生活能力の低下があり、介護予防のための支援が必要。
・要支援2
要支援1よりも、基本的な日常生活能力がわずかに低下した状態。
機能の維持や改善のために、何らかの支援が必要。
・要介護1
立ち上がりなどに支えが必要になり、歩行も不安定に。
排泄や入浴などの生活の一部で介助が必要な状態。
・要介護2
立ち上がりや歩行が自力では困難になり、排泄や入浴などで多くの介助が必要になる。
調理、金銭管理などに不安が表れるケースもある。
・要介護3
立ち上がりや歩行などが自力ではほとんどできず、排泄、入浴、衣類の着脱など生活全般に介助が必要。
物忘れなどが進む。
・要介護4
日常生活能力全般が低下し、食事や排泄、入浴、衣類の着脱などに全面的な介助が必要。
理解力の低下、問題行動が表れることも。
・要介護5
日常生活や身の回りの世話などの全面的な介助が必要。いわゆる寝たきりの状態。
記憶力、理解力の低下、問題行動が表れることもある。
③申請と併せて、ケアマネジャーを選定
実際に介護保険サービスを利用するには、要介護度に応じた介護サービス利用計画(ケアプラン)を立てる必要があります。
それを担うのがケアマネジャーです。
自治体の窓口や地域包括支援センターでは、「指定居宅介護支援事業者一覧」をもらえるので、そのリストからケアマネジャーを選定します。
一口にケアマネジャーといっても、居宅介護支援事業所のほか、特別養護老人ホームや民間の介護サービス施設など、所属先はさまざまです。
また施設介護に詳しい人、在宅療養に詳しい人など、得意分野が異なることもあります。
ですから、リストに載っている居宅介護支援事業所に電話連絡や訪問をして、在宅療養をしたいという希望を伝えて、対応してもらえる人を探すといいでしょう。
なお、ケアマネジャーと利用者は自由契約という関係になるので、介護保険サービスの利用を始めてから、方針などが「合わない」と思ったら、ケアマネジャーを変更することもできます。
それを担うのがケアマネジャーです。
自治体の窓口や地域包括支援センターでは、「指定居宅介護支援事業者一覧」をもらえるので、そのリストからケアマネジャーを選定します。
一口にケアマネジャーといっても、居宅介護支援事業所のほか、特別養護老人ホームや民間の介護サービス施設など、所属先はさまざまです。
また施設介護に詳しい人、在宅療養に詳しい人など、得意分野が異なることもあります。
ですから、リストに載っている居宅介護支援事業所に電話連絡や訪問をして、在宅療養をしたいという希望を伝えて、対応してもらえる人を探すといいでしょう。
なお、ケアマネジャーと利用者は自由契約という関係になるので、介護保険サービスの利用を始めてから、方針などが「合わない」と思ったら、ケアマネジャーを変更することもできます。
要介護認定は、一定期間ごとに見直しが行われる
要介護の高齢者は、時間の経過とともに状態が変わっていきます。
そのため要介護認定には12~24カ月の「有効期限」があり、一定期間ごとに見直しが行われます。
初回申請では原則12カ月ですが、状態が落ち着いている人は24カ月と長くなることもあります。
期限後も介護サービスを継続したいときは、期間にかかわらず更新の手続きが必要です。
また期限内であっても、高齢者の状態が悪化したときは、要介護度の変更の申請をすることができます。
そのため要介護認定には12~24カ月の「有効期限」があり、一定期間ごとに見直しが行われます。
初回申請では原則12カ月ですが、状態が落ち着いている人は24カ月と長くなることもあります。
期限後も介護サービスを継続したいときは、期間にかかわらず更新の手続きが必要です。
また期限内であっても、高齢者の状態が悪化したときは、要介護度の変更の申請をすることができます。